| コラム 「食品開発×SDGs」 | ||
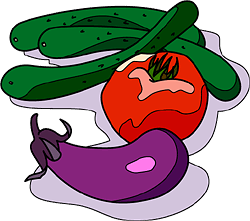 |
| コラム 「食品開発×SDGs」 | ||
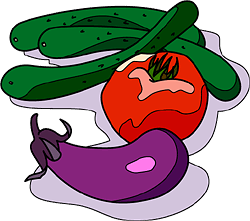 |
| (1) 食品ロスは“負債”ではなく“資源” | ||
| ~サスティナブルな食品開発のススメ~ | ||
|
皆さま、はじめまして。株式会社Agritureの小島(コジマ)と申します。当社は、規格外野菜や収穫余剰などの未利用資源を原料とした乾燥野菜・果物の製造を手がけており、「食品ロス削減」と「地域農業の持続可能性」の両立を目指しながら、国内外でサスティナブルな食品づくりに取り組んでいます。
ありがたいことに、全国の農家さんや企業様とのご縁をいただきながら、“まだ美味しく食べられるのに廃棄されていた食材”に新たな命を吹き込む加工技術と仕組みづくりを進めてきました。
そして、今回この「食品OEMコム」の読者の皆さまにも、サスティナブルな食品の可能性について少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。
さて、第1回目のテーマはこちらです。 「食品ロスは“負債”ではなく“資源”|サスティナブルな食品開発のススメ」
たとえば、京都府内で長年野菜を作ってきたB農園。伝統野菜の栽培を続けてきましたが、形や色が規格から外れたというだけで市場に出荷できない野菜が日々発生していました。収穫のたびに「これはもったいないけど、しょうがない」とため息をつく日々。
そんな折、私たちが提案したのが「乾燥野菜によるアップサイクル加工」でした。
この「サスティナブルな食品開発」を推進する理由は、市場が今まさに“変化と拡大”のフェーズにあるからです。
中でも、フードロス削減やフェアトレード、オーガニック、アップサイクル食品といった切り口は、明確な“購買動機”として消費者の心を動かしています。
とはいえ、大手メーカーがすぐに参入できる分野でもありません。調達の不安定さ、手作業の多さ、スケールメリットの出にくさといった側面から、大規模企業よりも地域密着型の中小メーカーの方が柔軟に対応しやすいという特長があります。
まさに、サスティナブル食品とは“中小メーカーが勝てる土俵”なのです。
また、WEBを活用すれば、環境意識の高い企業やカフェ、百貨店、自治体など、全国各地の“共感してくれるパートナー”とつながることも可能です。
私たちはこの動きを「サスティナブルOEM事業」と呼んでいます。
日本の人口は減少し、高齢化も進んでいます。これは食品業界にとって「胃袋の数」だけでなく「胃袋のサイズ」も小さくなっていくという二重のリスクを意味します。
そしてその答えの一つが、「社会や環境に配慮した商品をつくること」であり、同時にそれを“売れる商品”として設計・販売していくことにあります。
これからも「つくる人」「つかう人」「つなぐ人」の架け橋として、微力ながら貢献できれば幸いです。
Agritureの取り組むサスティナビリティについて : https://agriture.jp/sustainable/ |